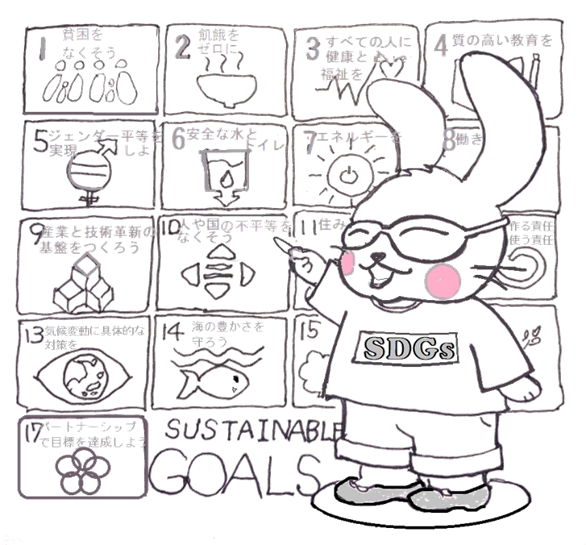
発行日 2022年10月
編 集 JHDN事務局
発行元 日本ハンチントンネットワーク
目 次
◇ ごあいさつ + オンライン交流会のご案内
◇ オンライン交流会・総会の報告
◇ 新入会者の自己紹介 (会員限定)
◇ 会員だより ♧ みんなの近況(会員限定)
◇ HDBuzz
◇ 【保険業界での遺伝情報の扱いについて】武藤香織
ごあいさつ
加瀬 利枝(あにどる)
みなさん、こんにちは。お元気ですか? 今年もまた大雨や大きな台風で大変な水害が発生してしまいましたね。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。これも人間が引き起こした地球温暖化の影響の気候変動でしょうか。環境を守ることも私たちの義務です。
そして、JHDNの会員さんと、そうでないみなさんも、ともに平和で心穏やかな生活ができますように、お手伝いできるように努力しています。心が元気でありますように。
オンラインWEB交流会のご案内
日時:2022年12月18日(日)14時~16時
プログラム
〇講演会「介護と福祉サービス」
〇グループワーク
※ 電子メールアドレスを事務局にお知らせくださっている方の中で、事務局からの電子メールが届いていない方は、members@jhdn.orgからの電子メールを受け取れるように、フィルターを解除してください。
WEB交流会の報告①
マキ
2022年度第1回目の交流会は5月14日(土)14時-16時にZOOMアプリを使って、インターネット上の会議室に集まりました。前半は講演会、後半はグループに分かれておしゃべり会の2部構成です。参加者は講師やボランティアを含め29名(うち初参加2名)でした。
講演会では大阪急性期・総合医療センター/大阪難病医療情報センターの難病医療コーディネーター看護師の野正佳余(のまさかよ)様より「ハンチントン病を患う人の入院・転院調整とそのポイント~難病相談の事例から~」というテーマでお話をいただきました。
よくある相談事例として「患者本人が嫌がって病院に行きたがらない」ときの医療福祉従事者としての対応ポイントは、①患者が入院を急ぐ病状かどうか ②患者に関わる家族たちの情報や認識に差異はないかの確認 ③それぞれの立場に配慮しながら情報収集 ④患者本人の思いを聞き取る、などが挙げられていました。これは私たちが相談にのるときにも重要なポイントですね。
また、厚労省は「患者と血縁のある家族・親族は自身が持つ遺伝に対する悩みや健康相談あるいは健康診断等の体調管理、発症者への対処方法など、予防的観点から、身近な医療機関等で早期から相談、支援ができる体制を構築することが望まれる」と考えて体制を整備しており、野正様のような難病医療コーディネーターや遺伝カウンセラーの体制の更なる充実が望まれます。
2つのグループに分かれてのおしゃべり会では「病気の告知」をテーマに話し合いました。参加者からは「自分たちの内なる差別で『告知』という壁を作っていたことに気づいた。自然に話していくことなのだと思った。」、「知らないでいる権利もあると思う。今の医療は治療法よりも診断確定が先行している。20歳まで待ってあげてもいいと思う。」などの意見がありました。
最後になりましたが講師の野正様をはじめ、グループワークで書記をしてくださった賛助会員の大賀様、松川様には心よりお礼申し上げます。

WEB交流会の報告②
マキ
2022年度オンライン総会の報告
2022年7月3日にオンラインで36名の会員や支援者らが集まり、総会が開催されました。
うち2名が初参加でした。
まず、総会では昨年度の活動報告・会計報告を行い、昨年度決算と次年度予算の承認を受けました(総会資料一式)。コロナの影響で集合形式での総会開催ができていないことや、メールやホームページなど電子化により、会員に情報を十分周知できていないことを心配するご意見もありました。引き続き、電子媒体だけでなく、紙媒体も併用しながら会員周知を図っていきたいと思います。また京都大学大学院の遺伝カウンセラーコースに所属されている大澤春萌さんからインタビュー調査への協力依頼があり、調査内容について説明していただきました。

講演会の前半は、国立精神・神経医療研究センター特命副院長・脳神経内科診療部長の髙橋祐二先生より「ハンチントン病の臨床と研究」についてお話いただきました。ハンチントン病の歴史から始まり、不随意運動については、額のシワや舌の出し入れや乳しぼりの手など、画像でわかりやすい説明があり、「早期からのリハビリが重要」「少し肥満気味の方が症状の進行が遅くなる」「喫煙量が多いと発症年齢が早くなる」など最新の研究に基づいた知見が示されました。また同センターで過去5年間に実施した遺伝カウンセリング33件のうちHDは4件、発症前診断に至るのは全体の6割で、中断したりや検査を受けない方も4割いることが分かりました。治療法については核酸医薬の実用化が他疾患で進んでおり、今後HDだけでなく遺伝子疾患全体の治療に結びつくことが期待されました。一方で安全性や高額な費用が課題となっています。
遺伝的リスク告知と結婚出産の意思決定―ハンチントン病を手がかりに
河合香織氏

講演会の後半は、東京大学大学院学際情報学府の河合香織様より「遺伝的リスク告知と結婚出産の意思決定―ハンチントン病を手がかりに」についてお話いただきました。
親子間で告知する際には子へ正しく伝えられるかどうかや、親の結婚生活がロールモデルになること、またアトリスク者が結婚するにあたり相談相手として医療従事者を選ばないこともある点を指摘されていました。また当会の相談事例では親からアトリスクの子や、アトリスクから結婚相手に対して結婚前に遺伝的リスクを打ち明けることを推奨しています。しかしそれは患者会の経験知であって、がんの家族歴や保有財産や出自を必ずしも開示しないのと同様に、「結婚相手へアトリスクであることの告知が強制されるべきものではない」ということを改めて認識しました。
交流会では
交流会では1グループ8名前後に分かれてグループワークを実施しました。患者・アトリスクグループ、介護者・支援者グループに分かれ、ご自身の悩みや経験を話し合いました。遺伝子検査を受けた経緯についても様々な理由がありケースバイケースだと実感しました。 最後になりましたが、お忙しいなか講演だけでなく交流会にもご参加くださった、高橋先生をはじめ、グループワークのファシリテーターや書記として協力してくださったボランティアや会員の皆様に深くお礼申し上げます。
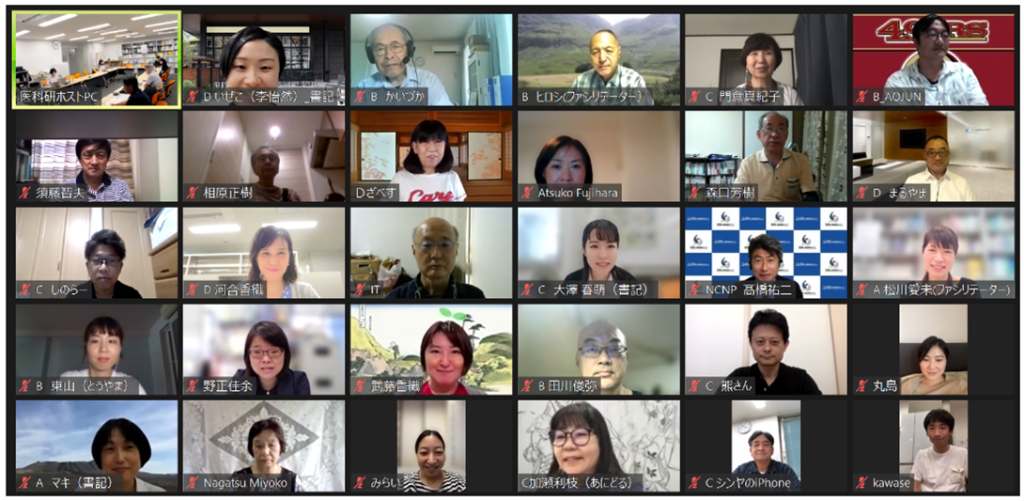
新入会者の自己紹介・マーシーさん
入会の経緯
今から約18年前に主人がこの病を発病しました。その時、一度ネットで検索してこの会の存在を知りましたが入会する気持ちにはなりませんでした。不治の病ということからくる絶望感、現実の生活をどうするか等、毎日に追われる自分には関係ないことだと思うようにしました。
夫の死後、二人の娘は遺伝子検査をある大学病院で受けました。次女が遺伝子を持っていました。今年で32才になり、昨年症状が出てきたように思え、一時、会社を3ヶ月休職しました。あまりにも早く症状がでてきたようで混乱しました。今回は経験もあるので、この病気に正面から取り組んでみようと思ったのが入会の理由です
困りごと
将来、誰が彼女をどこでケアできるのかが問題です。長い闘病生活が強いられる病気だと思うので心配です。
介護・療養の工夫
まだ必要としていないので、特にありませんが、将来どんな選択肢があるのか事例を紹介していただきたいと思います。
2月のオンライン交流会に参加して
各人が抱えている状況がそれぞれ違っていて一概に言える感想はありませんが、大変な病気だと痛感しました。

会員だより  みんなの近況
みんなの近況
このコーナーは会員のみなさまから寄せられた近況をご紹介します。
今回は2022年3月から9月に事務局に届いたもののうち掲載許可をいただいたものです。
※ 紙面の都合でハンチントン病はHDと表記しています

★MFさん:妻の純子は2020年2月17日に病院で誤嚥性肺炎で亡くなりました。発症してから12年でした。いろいろありがとうございました。亡くなる半年前ぐらいは 歯ぎしりがひどく口から血を出していました。マウスピースをと思いましたがのどにつまると言って病院ではだめでした。今は世話をやく人がいないので、とっても・・・
[コメント]:奥様は2年も前に亡くなられたとお知らせを頂きました。心よりお悔やみを申し上げます。奥様の介護は長年続き、日常的になっておられたと思いますが、その日常がスッポリと穴が空いたようになくなって、寂しい思いをなさっておられることとお察しいたします。これからはご自分を甘やかして好きなこと、やりたかったことなどを楽しめますように。奥様のご冥福をお祈り申し上げます。合掌(あにどる)
★ピャチャさん:特に変わりなく 入院先でも落ち着いているようです。
[コメント]:毎日、穏やかな療養生活で安定していらっしゃるご様子で安心しました。(あにどる)
★Kおばさん:元気です。
[コメント]:私たちも元気でーす! いつまでもお元気で、また近況報告送ってくださいね。(あにどる)
★NFさん:不幸とは続くもので、私は今年2月脊髄損傷により要介護5の身になってしまい、唯一、子の面倒をみるのが生きがいであったのに、それをも奪われ、毎日死にたい〃の連続です。
交流会には参加したかったのですが、そういう環境が整備されていないので、ぜひコロナもにらみつつ対面形式の会を行ってください。現在はリハビリ病院に入院中で7月退院です。(少し認知もあるかも)
[コメント]:大変なお怪我をなさって後遺症も残ってしまったこと残念ですし、心配しております。対面での交流会が出来なくて残念でたまりません、何か方法を考えてお話を伺えればと思います。お大事になさってくださいね。(あにどる)
★KKさん:息子と娘が母親の遺伝で検査結果でHDの確定診断を受けております、娘は長野県に住んでいますが、2か月に一回、A病院のB先生の診察を受けています。長野県から夫に車で送ってもらえています、息子は現在、B先生のご紹介をいただき、C病院で寝たきりの胃ろう治療を受けています、残念ながらもう退院は不可能かと思っています、私も79歳になりました、いつまでお付き合いできるか、心配ですが息子より先に死ねません、頑張ります、先日、読売新聞の1面に武藤香織先生のお写真を拝見しましたが、お変わりなくお美しく拝見いたしました、今後とも宜しくお願いいたします。敬具
[コメント]:お子様がおふたりとも重症になってしまったのですね。とてもご心配かと思います。お父様が頑張っていらっしゃるから、お子様も離れてはいるけれど頑張れるのかなと思います。私たちも遠くから応援しております。長生きしてお互いに支え合っていけることを希望します。
武藤香織先生も皆さんの近況には目を通しておりますので一緒に応援していますよ。(あにどる)
★NCさん:娘は現在も病院において頂いております。なかなか会わせて頂けないです。看護婦さんに様子をうかがう様にして帰ってくる、程度です。娘のお兄さんも、同じHDになったものですから、現在は施設に入所させて頂いております。
[コメント]:病院に預かって頂くのは安心ですが、会えなくて顔も見られないのは不安ですよね。お兄様も発症して施設での療養とのこと、おふたりとも穏やかな療養生活でありますようにお祈りしております。(あにどる)
★マキさん:いつも会員の皆さんからの近況報告を楽しみにしています。皆さんご苦労や工夫が、他の会員さんの励ましになっていると思います。
コメント:ひとりじゃないですもんね。立場は違えども同じ病気と共に人生を歩んでいる間柄、これからもお互いに支え合いましょうね。(しのらー)

★しんやさん:妻の面会が再開されました。1回/週15分です。先日、2年ぶりに家族全員で面会して来ました。息子の顔が見られたのでうれしそうでした。状態は落ち着いています。
[コメント]:奥様も同じ気持ちだと思います!(しのらー)

★gohanさん:入院している患者さんとのオンライン面会でLINEを使うようになりました。しかし一度も使ったことがありません。予約条件の、一日何名とか第二第三○曜日、面会時間午後○時とか、そこが埋まっていれば予約出来ません。また、入院患者さんは高齢者ばかりで、配偶者も高齢です。若い家族がLINEのお手伝いをしないと利用出来ないでしょう。
[コメント]:ITが苦手な高齢者でも使いやすい仕組みを考えて欲しいですね。(マキ)
★FAさん:今月初旬に3カ月ごとの診察を受け薬が1錠増えました。本人的には手の震えが少しおさまっていて生活がしやすいと言っています。何より嬉しい言葉です。
[コメント]:お薬が増えたので効き目があったのでしょうか、生活が楽になって本当に良かったです。このままの状態が続きますようにお祈りしておりますね。(あにどる)
★しのらーさん:妻の病状は変わらず、安定しております。寝たきりになってしまい、外出も出来ない為、なるべくベッドサイドには季節が感じ取れるものを置いています。
5月は子供の日、母の日があるので小さめの鯉のぼりやカーネーションなどのお花を置く予定をしております。
[コメント]:なんて優しいお気遣いでしょう。寝たきりでも目で感じられる季節はどんなものか?奥様に訊くことが出来るといいですね。(あにどる)

★KYさん:介護している娘の体調は良好で、娘の夫や孫も休日には来てくれて平穏な状況です。今の状態のうちに根本的治療に繋げたいと念願しています。
[コメント]:娘さんの体調が安定していらして安心しました。根治療法が一日でも早くできることを皆で願っています。(あにどる)
★TTさん:患者本人は転倒による恥骨骨折で入院中です。
[コメント]:転倒による骨折は大変なお怪我でしたね。早いご回復をお祈りいたします。
痛みはいかがでしょうか?心配です(あにどる)
★アッコさん: 主人の入院先と娘のこれから先をどうしたらいいのか悩み中です。
[コメント]:2人の患者さんのお世話は大変なことと思います。いつもオンライン交流会に参加してくださりありがとうございます。少しでも息抜きになっていればと思っております。(マキ)

★AOJUNさん:SNSを通じて国外を始めとした遠方の方と連絡をする機会が増えました。それぞれの治療や新薬の情報交換は勿論ですが、国や地域、信仰する宗教は違っても、人の命や人権・尊厳の大切さをHDを通じて改めて学ばせて貰っています。
[コメント]:素晴らしい活動ですね。もし宜しければ情報の共有をお願いいたします。(あにどる)
★こっぺさん:娘の症状はここ1、2年でかなり進行しています。歩行は補助して数分がやっとで、食事は全面的な介助が必要になりました。飲み込む時に喉に詰まらせることが何度かあり、慌てました。不随意運動だけでなく、随意運動の障害が問題に感じます。発声も、何か意識して言おうとする時は聞き取れないことが多いです。
身体的障害が出る前は、情緒不安定などの精神障害が顕著でしたが、最近は精神的には比較的安定しています。生きていても仕方ない、などと言うことも殆ど無くなりました。意外と思われるかもしれませんが、筋トレと有酸素運動が良かったのかもしれません。身体的トレーニングが精神に及ぼす好影響は最近脳科学により明らかにされつつあるようです。治療としては、コレアジンや抗精神薬を数種類飲みましたが、副反応が強くて中止しました。不随意運を抑制しても認知機能に悪影響があるという報告もあるようです。飲んでおられる方も多いと思いますので、情報交換が必要かもしれません。
[コメント]:筋トレや運動などのリハビリはとても有効だと髙橋先生の講演会でもお話がありましたね。薬の効果や副作用は兄弟でも個人差があるそうなので、家族が患者さんの変化を注意深く観察する必要があると思います。(マキ)
★IMさん:亡くなった兄の家族(妻、娘2人)・母・妹(私)皆変わらず元気に暮らしています。
[コメント]:皆さんお元気でお過ごしなのですね、お兄様は残念でしたが、ご家族がお元気で過ごされるとお兄様も周囲も安心です、私たちも見守っていますよ。(あにどる)
★森口さん(支援者):終活を始めています
[コメント]:終活はぜひやっておきたいですね、それに老いらくの恋も大切ですよ。(あにどる)
★TAさん:息子は若年性HDで、中学生の時に痙攣で発症が発覚しました。徐々に進行中。介助歩行を数メートル可能以外は全介助です。
[コメント]:日々の介護、精神的にも肉体的にもご苦労をお察しいたします。福祉支援をフルに使って、ご自分も大切に思いやってあげてください。(あにどる)

★ざべすさん:妹は、その後、サ高住に入所しました。感染症対策でなかなか面会できませんが、月1回はなんとか会えています。久しぶりに会うと、あまりにも母に似てきていることに毎回衝撃を受けます。病状も、ようやく落ち着いてきました。本当に大変な時期は3~4年間。これをどう乗り越えるかがHD療養のカギですね。マニュアルなどできればいいのですが、症状の軽い人とその周囲の方々にとっは脅かすことになりかねないのでなかなか難しいです。良い案があれば。
[コメント]:サ高住とは「サービス付き高齢者向け住宅」のことですね。
預け先を探し回って、こちらに落ち着いて一安心。マニュアル、私たちで作りたいですね。(あにどる)
【2022年6月以降にいただいた近況です】 ※投稿者の重複あり
★TYさん:先月から精神科で認知症の薬を試しましょうと「メマリーOD錠5mg」を処方されました。飲んだからと良くもなく、悪くも無くと思っております。患者本人の希望でツムラ芍薬甘草湯とツムラ葛根湯を処方してもらい、1日3回好んで飲んでいます。病は気からと言いますが、ツムラの2種が本人とても体に良いと思い込んでいますので、良いことだと思っております。ハンチントン病の為だと思いますが、お茶やお水を飲むときに空気と一緒に飲んでいるのでゲップをすると「ホッと」します。欧米ではゲップはタブーとされていますが、赤ちゃんと同じだなーと感じています。本人曰く、最近「呑み込みが悪く、のどに詰まる」と…。病気が進行しているのかなぁ~と思っております。本日私は1泊2日で大腸ポリープ切除の為入院!!
患者を1人にするのでとても不安ですが、入院の事はきちんと理解させ(理解させるまでが大変でした)、患者本人はとても興奮しています。何とか一日頑張って!!と思っております。
[コメント]:このような細かな情報をいただけると、いろいろ助かりますし参考になります。食事中のゲップはすごく共感! 無事に退院されましたか?(ざべす)

★tsfishさん:月一回の神経内科通院と心療内科およびカウンセリングで療養しています。ここ2ヶ月ほど家族以外の人、学生時代の友人や仕事関係の友人たちと交流を深めています。少し、ハンチントン病についても話せるようになってきたので以前より自分でも受け止められる部分が出てきたのかと思えることが少し増えました。
コメント:年を取ることは悪いことばかりじゃないですよね。物事を俯瞰できてくると、余裕ができてくるし楽しむことができてくる。目指すはカワイイ大人です。(ざべす)
★KYさん:娘の体調は比較的順調で落ち着いていますが、不随意運動は少しずつですが進行しています。根本的治療に辿り着けるまでこの好調状態を維持したいと思っております。
[コメント]:一日も早く根治療法ができるようにと毎日〃心から祈っています。研究職の方のモチベーションが上がるようなこと、なにかできないか探しています。(ざべす)

★たーちゃん:コレアジンをごく少量から飲み始めました。父がHDで、コレアジンの治験を受けました。その後、副作用なのかよくない時があり、コレアジンに対してかなりの抵抗感があったのですが、自分でも不随意運動が気になりだしたので飲んでみることにいたしました。
まだ、3日目ですが、一錠の半分でも、不随意運動は少し改善されてます。
副作用の強いクスリと聞いているので、飲まれている患者さんが実際どうなのか知りたいです。
[コメント]:いつも前向きな たーちゃんの姿にみんな励まされています。コレアジンですが結果の良し悪しがそれぞれみんな両極端でなんとも言えないので、もっと情報を集めたいと思います。ご協力をお願いしますね(ざべす)
★しのらーさん:今はねたきりで、ほとんど意味のある言葉を発することが出来なくなっている家内ですが、先日、久しぶりに短い会話ですが、やりとりがあったようです。脳神経学について門外漢の自分ですが、その日は何もがうまく繋がったのかなと思います。その当事者が自分でなかったのは、すごく残念ですが、いつどのタイミングでまた再び、その奇跡がやってくるか判らないので、その奇跡を信じて日々、支え続ければなあと思います!
[コメント]:医学的にどうとか、一般的なことは超越している疾患なので、きっとその日はまた来ます! その場に居られたらどんなに嬉しいことか。愛も深まると思います♡ (ざべす)
★shibuさん:当事者本人は今回も誤嚥性肺炎で昨年暮れから1ヶ月程入院加療となりました。原因は良く解ってません。嘔吐が2~3日続いて診察、検査となりその後脱水状態で緊急入院加療。胃部の圧迫かと考えエアマットを取り換えたのが良かったかもしれません。今は何とか回復し落ち着いています。私といえば、利用している皆さんと同様コロナの影響で施設入館制限継続のため15分の別室面会のみです。脳神経に関わる人のケアは全てとは言いませんが日常的な精神的刺激が大きな比重を占めると思っています。それがなかなか出来ないでいるのが一番もどかしいところです。利用している施設の人には出来るだけ小まめに声掛けや接する機会をつくって貰うようにお願いしています。家族のようには行きませんが。そんなことで少々デジタルに時間を割いて半年前にスマホデビューし、いろいろと使いこなせるようにとオンラインの歩みを始めました。もうしばらく掛かるでしょう。
[コメント]:誤嚥性肺炎からの復活、さすがです! みんなで参考にしたいと思います。交流会のためにzoomデビューに向け尽力される姿は、後に続く人たちを増やすことにつながっているのでます。(ざべす)

★KKさん:定期的に通院を同伴で行ってますが、母親のわたしが倒れたら先はどうなるの…
家事支援とかは皆様はされているのでしょうか?また難病申請はされているのでしょうか?
[コメント]:HDと診断されたのでしたら、指定難病受給者証の申請をしてくださいね。介護保険が申請できるかどうか包括支援センターなどで訊いて、ヘルパーさんに家事支援をお願いすることができますよ。ひとりで抱え込まないでくださいね。(あにどる)
★IMさん:それぞれ元気に暮らしております。ただ、兄が亡くなり年々明らかに義姉とは疎遠になって来ています。姉がいつで話を聞いてもらえる相談者に恵まれていれば良いなぁと願っています。
[コメント]:義姉さまとは疎遠になってしまっておられるのですね。それでも気にかけてくださっているお気持ちが伝わると良いのですが。IMさんもお身体ご自愛くださいませ。(あにどる)

★NMさん:要介護者は落ち着いて暮らしています。要介護者のニーズに合った車椅子になかなかヒットできないのが、今の最大の悩みです。
[コメント]:10月に「福祉機器展」がありますのでパンフレットを手に入れます。車椅子の業者に来てもらって調整してもらうという手段もありますよ。(あにどる)
★IMさん:娘がハンチントン病と脊髄小脳変性症との合併症です。来週、胃瘻の手術となります。誤嚥性肺炎の死亡が増えていると聞き手術を了解しました。”
[コメント]:誤嚥性肺炎は心配ですよね、胃ろうを造ってもお口からも食べることが出来ますので、工夫して、たまにでもいいからお口から食べて頂けると良いなと思います。(あにどる)
★FAさん:2年前に診断されてから大きく進行はしていませんが、手の震え、強張りの状態は日によって違うようです。息子も『調子が良い時と悪い時があるから…』と状態を受け入れて毎日穏やかに過ごせています。我が息子ながら尊敬します。近所の公園までを20分くらいランニングするのが日課で、先月は就労支援事業所の仲間、スタッフの方々と高尾山にも登ってきました。みんなから体力あるねと言われて嬉しかったようです。このまま進行がゆっくりであって欲しいと願っています。早く治療薬、治療法が見つかることをただ願うばかりです。
[コメント]:ランニング・登山、楽しそう、素敵ですねぇ。事業所に通所していること自体がリハビリになっているので進行も抑えられます。頑張ってー-!応援していますよ。(あにどる)

★MMさん:父親がハンチントン患者です。結婚することになり、子供を持つかどうか考えるために遺伝子検査を受けようと考えています。
[コメント]:結婚をきっかけに発症前遺伝学的検査を考える方は多いと思います。ただ、陽性という結果がでたらどうするのか、パートナーの方とお話し合いのうえ、MMさんご自身のお気持ちを大切に決めてくださいね。(あにどる)
★アッコさん:主人が入院して娘の介護に従事しています。
[コメント]:介護には福祉支援をフルに使って、ご主人と娘さんを診てあげてくださいね。(あにどる)

★ATさん:娘がほぼ寝たきりの状態で、付ききりで観なければならないのです。
[コメント]:ヘルパーさんにお手伝いしてもらっていますか?ケアマネさんと話し合い、ご自身のことも大切に考えてあげてくださいね。(あにどる)
★FSさん:現場の仕事を離れて7年。療育センターの利用者の訃報が相次いでいて心が痛みます。ご家族から医療側の対応に不信感を持つケースが多くコロナ対応があったとはいえ、明らかに命の選別が行われている現状に怒りを覚えます。
[コメント]:お怒りはごもっともです。患者家族の立場として同じ思いをしたことがあります。医療者との対話が上手にできると良いのですが。「対話」の勉強会をしたいですね。(あにどる)

「遺伝子治療に関する先日のプレスリリースを紐解く」より抜粋
執筆:レオラ・フォックス博士、サラ・ヘルナンデス博士 編集:ジェフ・キャロル博士
この記事はHDBuzzのホームページに2021年8月16日に掲載された英文記事を会員有志が日本語に訳したものの抜粋です。出典:https://en.hdbuzz.net/310 また、JHDNのホームページには最新情報も加味した全体版が掲載されています。
ボイジャーセラピューティクス社は遺伝子治療における送達(薬を投与するプロセス)に新たな技術を追求することとなり、予定していたHDの臨床試験を取りやめました。ただ、長期的にはこれによって、もっと侵襲性の低い薬ができるようになるかもしれません。また、他にもたくさんの企業がHDの遺伝子治療に取り組んでいます。
遺伝子に関する知識の簡単なおさらい
DNAは設計図になぞらえることができます。すなわち、個体内にあるあらゆる細胞の遺伝子レベルにおける基本設計図なのです。この基本設計図を真新しい状態に保つため、細胞はタンパク質を作るにあたってDNAのコピーを作業用に作成します。このDNAのコピーがRNAです。RNAはコピーにすぎないので、ぼろぼろになりはしないかとあまり気づかうこともなく使い倒すことができます。ぼろぼろになれば、細胞は設計図のDNAからコピーのRNAをまたすぐ作ることができます。
科学者はこうした知識をテコに巧妙な方法を編み出すことで、自らが着目しているタンパク質を細胞にたくさん作らせたり、あまり作らせないようにしたりしているのです。
ハンチンチン低下への応用
HDの場合、関心は細胞に損傷を与えるハンチンチンタンパク質の生成を減らすことにあります。これがいわゆるハンチンチン低下です。ハンチンチン低下には二通りの方法が可能となります。
1)生成されるRNA(=コピー)を破壊します。ただ、DNA(=設計図)はそのままにしておきます。これはアンチセンス・オリゴヌクレオチド(ASO)がよって立つ戦略で、ロシュ社やウェーブ社が臨床試験で試していたASOなどがそうです。
2)DNA(=設計図)からのメッセージを一部変更して、DNAをRNAにコピーできなくしたり、当該RNAの破壊に役立つ新たな指示を追加するようにしたりします。「遺伝子治療」と言う場合にはこのアプローチを指します。設計図自体は変えず、設計図から作られるものを変えます。
上記の二つの一番大きな違いは、RNA(=コピー)を破壊するにとどまる場合は投与を繰り返す必要があることです。細胞には依然としてもともとのDNA(=設計図)がありますから、新たなRNA(=コピー)が作られ続けます。したがって、そのコピーを常に破壊しない限り、ハンチンチンタンパク質が依然として生成されることになります。繰り返し投与するのは億劫に思えるかもしれませんが、このタイプのアプローチの場合、要するにRNAをターゲットにするだけの薬なので、その効果は必ず最終的には消え去るわけです。これによって安全面でのメリットはより大きくなります。
ハンチンチン低下における遺伝子治療アプローチ(ユニキュア社やボイジャー社が取り組んでいるアプローチもそうです)では、ハンチンチンを標的とするに際し脳細胞に対して遺伝子上の指示を一度伝えるだけです。その後この指示に従って脳細胞はハンチンチン生成に干渉することができるRNA分子を作り続け、ハンチンチンタンパク質レベルを下げることになります。これは一回限りで完了するタイプのアプローチなので、繰り返しの投与は必要ありません。けれども、注意すべきは、このアプローチの場合、ハンチンチン低下のせいで他の影響が生じたとしても後戻りはできないということです。
現時点でHDなどの脳疾患の遺伝子治療を行おうとすれば脳外科手術が必要になります。というのもDNAに手を加えるそうした薬は脳関門を突破することができないからです。この大きな制約こそ、ボイジャー社が回避しようとしていたものなのです。
開発途上にあるその他の遺伝子治療薬
HDの遺伝子治療分野のトップバッターはユニキュア社で、ウイルス(AAV)を使った治療薬(AMT-130)を開発中です。この治療薬の最終的な目的は、脳細胞に指示を伝えて特別なRNAを作らせ、これによってハンチンチン遺伝子に対応したRNAを見つけ出して破壊することです。このようにして、遺伝子治療薬はハンチンチン低下を恒久的にもたらすよう使用することができます。ユニキュア社は動物による研究を長年慎重に行ったうえで安全性試験を開始しました。
ウイルスを使ったハンチンチン低下の遺伝子治療薬の開発で臨床前の段階にある企業としてはさらにスパーク、サノフィ、アスクレピオスバイオ製薬(AskBio)などがあります。
ハンチンチン低下の遺伝子治療アプローチにはジンクフィンガーという新たな手法を使うものもあります。最近になって日本の製薬大手武田がサンガモ製薬(もともとこの薬を開発したのはこの会社です)からこのHD事業を引き継ぎました。ハンチンチン低下におけるこのアプローチの主たる利点は、変異ハンチンチン遺伝子だけを選んでそのスイッチを切ることができる点で、HD患者のほぼすべてが持っている正常な方の対立遺伝子は見逃してくれるのです。
今回のポイント
脳疾患への遺伝子治療の適用というのはHDとの闘いの試みの中でも最も最先端のアプローチです。新たな分野ではそれがどのようなものであってもいえることですが、ひとつの治療法に至る道には多くの紆余曲折が必ずあります。ボイジャー社が先日発表した最新情報は、その典型的な例です。今年中に予定されていた臨床試験が実施されないことになったのは確かに残念ですが、新たに開発した技術をボイジャー社がHD患者やその家族のために使おうとしているのは素晴らしいことです。他の企業も遺伝子治療の領域などで精力的に取り組んでいることからも分かるように、多くの本当に素晴らしい戦略がHDという課題に適用されているのです。
保険業界での遺伝情報の利用に関する共同声明と差別禁止法制に関する新たな動き
武藤香織
この春、長い間、国内でルールが決まっていなかった、遺伝情報に基づく差別に関して、新たな動きがありました。ここでは、今日まで続く様々な動きをご紹介します。
日本医学会と日本医師会による要望
2022年4月6日、日本医学会と日本医師会は、合同で記者会見を行い、「遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止」についての共同声明を発表しました。共同声明では、様々な疾患を対象に遺伝学的検査やゲノム解析が進められている一方、遺伝情報を用いて本人や血縁者にとって不当な差別や社会的不利益を受けるリスクが放置されていると指摘しています。そのうえで、患者・家族だけではなく、現時点では遺伝との関連を自覚していない多くの健康な方々にも不安が広がる恐れがあるとして、次の3点の事項を要望しました。
① 国は、遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益を防止するための法的整備を早急に行うこと、及び関係省庁は、保険や雇用などを含む社会・経済政策において、個人の遺伝情報・ゲノム情報の不適切な取り扱いを防止した上で、いかに利活用するかを検討する会議を設置し、わが国の実情に沿った方策を早急に検討すること
② 監督官庁においては、遺伝情報・ゲノム情報を取り扱う可能性のある保険会社等の事業者及び関係団体に対し、遺伝情報・ゲノム情報の取り扱いに関する自主規制が早急に進むよう促すとともに、その内容が消費者に分かりやすく適正なものとなるよう、指導・監督を行う仕組みを構築すること
③ 遺伝情報・ゲノム情報を取り扱う可能性のある保険会社等の事業者及び関係団体は、遺伝情報・ゲノム情報の取り扱いについて開かれた議論を行い、自主的な方策を早急に検討し公表すること
保険業界の考え方も公表された
翌5月27日、保険会社の団体である生命保険協会と日本損害保険協会は、生命保険や損害保険での遺伝情報の取扱を、加盟各社に確認をしたうえで、医療従事者に向けて現状を説明する文書を公開しました。内容は、生命保険協会、日本損害保険協会ともに概ね同じです。
この文章では、保険に加入するとき、そして支払い請求をするときに、遺伝学的検査の結果(発症前検査と確定診断の検査の両方とも)を収集したり、利用したりしないし、医療機関から提出されたカルテの記録などに記載されている、遺伝学的検査結果、病名、家族の病歴なども使わない、研究として行われた解析結果も使わない、と宣言されています。
一方で、これはあくまでも当面の取扱いであって見直される可能性があること、自分が契約している保険商品での取り扱いがどうなるかは、個別に確認するようにと書かれています。
発症前検査を検討されている方は、これまで通り、検査を受けるよりも前に、余裕をもって保険に加入しておくことをお勧めします。 原文はこちら
超党派の国会議員による法案の考え方が公表された
一方、国会では、日本医学会と日本医師会の要望を受けて、10月6日に超党派の議員連盟が第8回総会を開き、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案大綱(試案)」をまとめました。これは、新たな法律の基本的な考え方や方針を示したものです。
基本理念は、
①ゲノム医療の提供及び研究開発の推進によって、世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できることとなるようにすること、
②子孫に受け継がれる可能性のある遺伝子の編集を伴うものその他の人間の尊厳の保持に重大な影響を与える可能性があるものも含まれることに鑑み、その各段階において生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること、
③生まれながらに固有で子孫に受け継がれる可能性のある個人の有する塩基配列情報には、それによって当該個人はもとよりその家族についても将来の健康状態を予測し得る等の特性があることに鑑み、ゲノム医療の提供に際して得られた塩基配列清報の保護が十全に図られるようにするとともに、塩基配列情報に係る不当な差別が行われることのないようにすることにより、国民が安心してゲノム医療を受けられるようにすること、で構成されています。
今後、与野党で合意し、法案として提出されるかどうか、また法律として成立するかどうかは未知数ですが、長い間、膠着状態にあった状態からみれば、大きな一歩を踏み出したと言えます。
そこで、学会や産業界、患者・家族団体など多くの団体とともに、超党派議連に法律の早期成立を目指す第一弾の要望書を提出することとなり、JHDNも賛同しました。要望書を同封していますので、ご覧ください。

<すべてのお問い合わせ先>
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1
東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター
公共政策研究分野内 JHDN事務局
事務局への電子メール jhdn@mbd.nifty.com
相談メール jhdn@mbd.nifty.com
<会費・寄付の振込先>
ゆうちょ銀行口座 記号10090 番号72610961
日本ハンチントン病ネットワーク
三菱UFJ銀行口座 高田馬場支店 (普)1348857
ニホンハンチントンビョウネットワーク
掲載された文章・イラストの無断転用は禁じます
